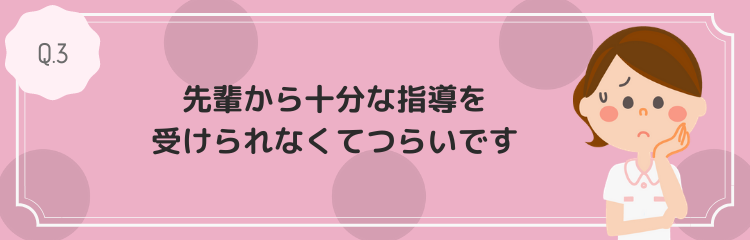Q3. 先輩から十分な指導を受けられなくてつらいです
私は短大を卒業し、循環器内科病棟に入職しました。
急性期患者の受け入れも多く、循環器患者だけでなく呼吸器内科や腎臓内科の重症患者の受け入れ先として、シビアな現状を目にすることも多い現場です。
しかし、看護師は若年層が多く、2年目が1年目を教えるのも当たり前という状況です。常に人手不足でちゃんとした指導を受けられず、「じゃあ、お願いね」と仕事を丸投げされることも多いです。
初めてする手技、初めて受け持つ重症患者、診療の補助…自分が教えてもらいたい立場なのに、学生指導もしないといけない…という環境です。
先日、リーダーから突然「悪いけど今日は、呼吸器がついている患者を受け持って」と言われました。でも私は呼吸器を装着した患者を受け持った経験はなく、もちろん事前準備もしていません。
何を観察したらいいのか、正常や異常、観察するときの注意点、何を申し送ればいいかなど、なにもかもわからないことばかり…。
情報収集をしたあとはマニュアルを見ながら必死にケアをしましたが、その日は本当に不安しかありませんでした。
他にも、突然「CV挿入や胸腔穿刺の診療の補助について」と言われたり…初めてなのに「もうそんなこと出来て当たり前でしょ」「できないじゃなくてやらないと」などと言われることもよくあります。
「出来てあたりまえ、やれて当然」の環境は本当につらいです。どうすれば良いでしょうか。
(循環器内科勤務 1年目 東京都)
看護師として「できる」ようになること
とても厳しい現場で働いていらっしゃるのですね。わからないことだらけの中、先輩から十分な指導を受けられないというのは、とても不安だと思います。
キャパシティをオーバーした仕事内容と、十分な教育がなされない状況へのストレス。出来てあたりまえ、やれて当然の環境はとてもつらいですよね。
このような厳しい環境では、「できないのがつらい」「わからないのが不安」というのが、一番大変なポイントです。
問題の根本は、充実した指導を受けられず知識が不足していることです。話を聞く限り、あなた自身に学ぶ力や応用力はあると思うので、そこさえ解決できれば、気持ちよく仕事ができるはずです。
そこでおすすめなのは、本やネット、動画を利用して勉強することです。自分で勉強して、知識を増やしましょう。
動画サイトなどで手技の確認をするのは手軽な方法なので、通勤時間などにチェックすると良いと思います。今は便利な世の中ですから、どんどん活用していきましょう。
心電図や呼吸器管理、透析患者の看護など、自分で勉強するには限界があるものもあります。本や動画等を見ても理解できない知識については外部の勉強会に参加するのもひとつの手ですね。
そして実践でできるようになるためには、自分が現場でおこなった内容と照らし合わせ、自分の職場で使っている物品に置き換えて手順書を整理することも、とても大切なことです。
忙しくても「相談」することに慣れる
「やったことがなくて不安です」
「初めてなので教えてください」
と、先輩看護師や先生に言えない、というのも問題のひとつですね。
先輩や医師に相談することは、新人じゃなくても看護師として絶対に必要なことなので、それを恥じる必要はまったくありません。
「できて当たり前でしょ」と言われてしまうということですが、先輩が落ち着いているときであれば、少しなら時間を割いてくれたり、丁寧に指示をくれることもあるのではないでしょうか。
相手を選んだり、タイミングを見計って、「先輩に相談する」ということに慣れていきましょう。冷たくあしらわれても、めげてはいけません。そういうことの繰り返しで、手技も知識も人並みの看護師になっていくのだと思いますよ。
自分で勉強するだけでは限界があります。素直な気持ちで「できない」「わからない」を伝えることで、わからないことは教えてもらうという、当たり前の環境ができてくると思います。
「看護師として成長したい」という気持ちが大切
現場はかなり厳しい状況のようですので、あまりにつらくて体調に異常をきたすようであれば転職も考えてみてくださいね。
ですが、もし今の職場でもう少しがんばっていきたい、と思われるのでしたら、
- 自分で勉強して知識を増やす
- 同期で練習・勉強・共有する
- わからないことは先輩にどんどん質問する
など、いろんな解決方法が考えられると思います。
一番大切なのは、「看護師として成長したい」という気持ちです。
綺麗ごとの「成長したい」じゃなくても良いんですよ。
- 先輩から怒られたくないから成長したい
- 先生に良いところを見てほしいから成長したい
- 楽に仕事をしたいから成長したい
など、そういう気持ちでも大丈夫です。
看護師は悩んで成長する仕事
新卒には新卒の、5年目には5年目の、10年目には10年目の悩みや不安があります。
何年看護師をしていたって、知っていて当たり前なんてことはありません。
知らないことを素直に受け止め、新しいことを取り入れようという姿勢は、どんなにベテランになっても忘れないようにしましょう。